すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
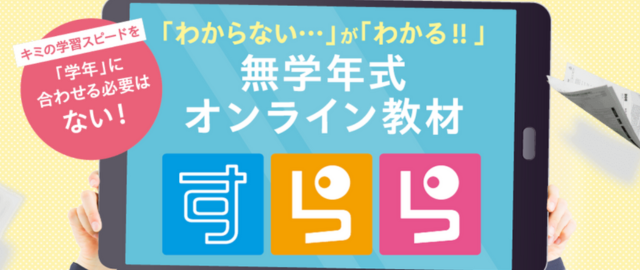
不登校のお子さんが自宅で学習していると、「この学習って学校の出席として認められるの?」と不安になる保護者の方も多いですよね。
すららは、文部科学省が定める「出席扱いの条件」に対応した教材のひとつであり、実際に多くの自治体や学校で出席扱いとして認められている実績があります。
もちろんすべてのケースで保証されるわけではありませんが、すららが提供するレポートや学習の継続性、計画性は、学校側にとっても「安心材料」になる要素ばかり。
このページでは、なぜすららが出席扱いになりやすいのか、その理由について具体的に解説していきます。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららは、学習内容の「質」と「記録の明確さ」を両立している教材です。
学校が出席扱いと認めるには、単なる自宅学習だけではなく、どんな教材を使い、どの程度の時間・進捗で学習しているかを客観的に証明する必要があります。
すららでは、学習ログが自動で記録され、保護者や学校側が確認できる「学習レポート」を提出することが可能。
これにより「家庭でサボっていたのでは?」といった疑念を抱かれることもなく、学校側にも納得してもらいやすくなります。
また、提出物として整っているため、先生にとっても対応しやすく、トラブルが起きにくいのもメリットです。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでは、学習時間や理解度・進捗などが自動的に記録されるので、そのデータをまとめた学習証明レポートを学校側に提出することで、出席扱いとして認定されるケースがあります。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
毎日の学習記録を手書きでつける必要はありません。
すららが自動で進捗を可視化してくれるので、保護者の負担も少なく、学校に対しても説得力のある「証拠」として提出しやすいのが特長です。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
不登校のお子さんにとって大切なのは、「自分に合ったペースで、無理なく継続できること」です。
すららは、無学年式という特長に加えて、プロのすららコーチが一人ひとりに合わせた学習計画を作成し、日々の学習を見守ってくれます。
この「個別最適な指導」と「継続的な学習支援」があることで、学校側にも「しっかり取り組んでいる」という印象を与えることができます。
計画性のある学習は、出席扱い申請において非常に重要な判断材料のひとつ。
本人の意思だけでなく、第三者であるコーチが関与していることも、大きな安心材料になります。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
単に教材を使うだけでなく、専門のコーチが継続的に学習サポートをしてくれることで、「ただの自主学習」ではないと学校に伝えられます。
計画的な学びは、出席扱いとしての信頼にもつながります。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
すららでは、学習のプロである「すららコーチ」が一人ひとりの学習進度や個性に合わせた学習計画を作成してくれます。
これにより、子どもだけでの自己管理が難しいケースでも、無理なく計画的に学びを進めることができます。
さらに、進捗の確認や声かけなども継続的に行ってくれるため、「続けられるか不安」という保護者の悩みも軽減されます。
こうした第三者の存在が、学習の継続性を支えてくれるのです。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
すららの無学年式学習は、子どもの理解度や苦手分野に応じて、自由に学年をまたいで学習できるのが魅力です。
たとえば、中学2年生でも、小学校レベルに戻ってやり直すことができますし、逆に得意な教科はどんどん先に進めることも可能です。
不登校の子にありがちな「勉強の遅れ」や「一部だけ得意・苦手の差が激しい」といった状況に対して、柔軟に対応できるため、焦らず自分のペースで進めることができます。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
すららでは、学習する本人と保護者だけで完結するのではなく、学校との連携を前提としたサポート体制が整っています。
具体的には、出席扱いの申請に必要な書類の準備、学習記録の提出、担任や校長先生とのやりとりの橋渡しなどを、すららがフォローしてくれます。
「こういう書き方で提出すれば通りやすい」など、実際の現場で蓄積されたノウハウをもとにサポートしてくれるため、初めての申請でも安心。
保護者がすべてを抱え込まなくてもよい体制があることが、大きな安心材料になります。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
出席扱いを申請する際の「何を出せばいいのか分からない」という不安に対して、すららは具体的な必要書類の説明や準備の手順をわかりやすく案内してくれます。
初めてでも安心して進められます。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
すららでは、すららコーチが学習レポートのフォーマットを用意し、必要な情報を自動でまとめてくれます。
学校へ提出する際の文言や提出タイミングについてもアドバイスがあり、提出までをしっかりフォローしてくれます。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
担任の先生や校長先生にうまく伝えられないというご家庭に対して、すららは「どう説明すれば伝わりやすいか」や「どのタイミングで相談すべきか」といった部分も含めてアドバイスを行ってくれます。
結果的に、家庭・学校・すららの三者が同じ方向を向いて支援できる体制が築けます。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、文部科学省によって「不登校支援教材」としても評価されており、実際に全国の多くの学校や教育委員会で採用されています。
この実績があることで、「すららで学んでいる=正式な学習活動である」と認められやすく、出席扱い申請の際にも有利に働くことが多いです。
単なる自習教材ではなく、文科省が後援・表彰してきた信頼性の高いプログラムであることから、学校側の理解を得やすいという強みがあります。
教材の信頼性は、出席扱いをスムーズに申請するうえでの非常に大きなポイントになります。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
全国各地の公立・私立学校や教育委員会で、すららが導入・採用された実績があります。
このことが、「家庭学習を学校とつなぐ」ための大きな後ろ盾となっています。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
文部科学省の支援のもと、不登校児童・生徒への支援教材として活用されており、その実績が出席扱いの信頼性を支えています。
すでに活用例があるため、学校への説明もしやすくなっています。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
出席扱いにおいて重要なのが「その学習環境が学校教育に準ずるものかどうか」です。
すららは、文部科学省の学習指導要領に準拠した内容で構成されており、教科ごとに体系立てられたカリキュラムで学ぶことができます。
また、学習の成果がデータとして記録され、定期的なフィードバックも行われるため、「ただやっているだけ」ではない質の高い学習環境として評価されやすいのです。
このような要素があることで、学校も安心して出席扱いとして認めやすくなります。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららで学ぶ内容は、小・中・高校の教科書レベルに基づいており、教科ごとの到達目標に沿って設計されています。
つまり「学校と同じレベルの学び」ができる仕組みです。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららでは、単元ごとにテストや診断が用意されており、それに応じて学習内容が変化します。
自動的に苦手を見つけ、克服させていく設計があるため、「評価される学び」として扱われやすいのです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
不登校のお子さんが自宅で「すらら」を使って学習を続けている場合、その学習が学校の「出席扱い」と認められる可能性があります。
これは、文部科学省が定める一定の条件を満たすことで、在宅学習を出席として認定できる制度に基づくものです。
ただし、すべてのケースで自動的に出席扱いになるわけではなく、学校や教育委員会への正式な申請が必要です。
このページでは、すららを使って出席扱いを申請するための具体的な手順や必要書類について、わかりやすくステップごとに解説していきます。
申請方法1・担任・学校に相談する
出席扱いの申請は、まず担任や学校とのコミュニケーションから始まります。
学校側も制度に詳しくない場合があるため、保護者から「すららで在宅学習をしている」「出席扱いの制度を検討したい」と丁寧に伝えることが大切です。
そのうえで、必要書類や条件を確認し、実際の申請準備に入ります。
早めに学校へ相談することで、手続きがスムーズになり、保護者の負担も軽減されます。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
学校により申請に必要な書類は異なる場合があります。
すららの学習レポートのほか、医師の意見書などが求められることもあるため、事前にチェックしておくと安心です。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
不登校の理由が体調不良や発達特性に基づくものである場合、医師による診断書や意見書の提出が必要になることがあります。
これは、「医療的な支援のもとで在宅学習が適している」ことを第三者の視点で示すためのものです。
診断書がなくても出席扱いになるケースもありますが、求められた際にはスムーズに対応できるよう、事前に医療機関と連携しておくと安心です。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
精神的なストレスや発達障害などが背景にある場合、学校側が客観的な証明を求めることがあります。
診断書があることで、制度の条件を満たしやすくなるケースもあります。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書には、不登校の状態や在宅学習の必要性、継続性について記載されていることが望ましいとされています。
必要に応じて、医師に具体的な要望を伝えることも大切です。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
出席扱いとして認められるためには、「家庭で継続的な学習が行われている」ことを客観的に示す必要があります。
すららでは、学習履歴や理解度などを記録した学習レポートをダウンロードできる機能があり、これを学校に提出することで、学習の質や量を証明できます。
提出の際には、すららコーチがアドバイスをしてくれる場合もあるので、不安なときは相談してみましょう。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららのマイページから、学習レポートや進捗データをPDFで出力することができます。
日付や教科別の学習量などが分かるため、非常に説得力のある資料となります。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
出席扱いを申請するための正式書類(申請書や同意書)は、学校が用意・作成する場合がほとんどですが、保護者が協力して記入や添付書類の準備を行うことが求められます。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
提出した書類や診断書、学習レポートなどをもとに、学校長が「出席扱い」として認めるかを判断します。
自治体によっては、教育委員会への申請・承認が必要な場合もありますが、その場合も学校が窓口になってくれることがほとんどです。
必要な対応は自治体や学校によって異なるため、担任や教頭先生と連携を取りながら進めるのがベストです。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
すべての書類が整い、条件を満たしていると判断されれば、最終的には校長先生の承認により「出席」として記録されることになります。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
自治体によっては、教育委員会の承認が必要なケースもありますが、その場合も学校側が書類を取りまとめて提出してくれるので、保護者は必要な部分だけをサポートすればOKです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
すららを活用して在宅学習を行い、それが「出席扱い」として認められると、実は子ども本人だけでなく保護者にとってもさまざまなメリットがあります。
単に「休みがちでも安心」というだけでなく、内申点の評価や進学への影響、さらには家庭全体の精神的な負担まで、幅広くポジティブな効果が得られるんです。
ここでは、出席扱いが認定されることによって得られる代表的なメリットを3つに絞って、わかりやすく紹介していきます。
「ただ勉強している」ではなく、「認められる学び」に変わることで、未来の可能性がグッと広がりますよ。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
出席扱いとして学習を継続していると、学校での「欠席日数」がカウントされにくくなります。
その結果、出席率が保たれ、内申点に対する評価も悪化しにくくなるという大きな利点があります。
とくに中学生の場合、高校入試では内申点が重要な判断材料になることが多いため、「出席=学ぶ姿勢がある」と認められることは非常に大きな意味を持ちます。
また、内申点が守られることで、志望校の選択肢を広げることができ、進路の幅が狭まらないのも安心材料のひとつです。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
すららでの学習が出席扱いになると、「休んだ日数」がカウントされないため、学習意欲の証明にもつながり、成績表の評価項目にも良い影響が出やすくなります。
中学・高校進学の選択肢が広がる
内申点が維持されることで、公立高校や推薦枠のある学校も選択肢に入りやすくなります。
「出席していないからダメかも…」という進路への不安を軽減できます。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校の子どもが感じやすいのが「自分だけが取り残されている」という焦りや不安です。
でも、すららで毎日コツコツ学習を積み上げ、それが出席として認められると、「ちゃんとやっている」「学校とつながっている」という安心感が生まれます。
遅れても自分のペースで学べること、そしてその努力が評価されるという流れが、子どもの不安や劣等感を和らげてくれるのです。
結果として、学びへのモチベーションも自然と高まりやすくなります。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
自分のペースで取り組めるうえ、苦手な分野も戻って復習できるすららなら、集団の進度を気にする必要がありません。
マイペースでも安心です。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
「どうせできない」という気持ちにさせず、「できている」「頑張れている」と実感させてくれる環境があることで、自信の芽が育ちます。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子を持つ親は、学力の遅れや進路の不安、学校との関係など、日々多くの心配事を抱えています。
でも、すららを活用して出席扱いとして認めてもらえることで、「このままでいいのかな…」というモヤモヤが少しずつ軽減されていきます。
また、すららには専任コーチがついており、保護者一人では抱えきれない部分もフォローしてくれるのが心強いポイントです。
学校との連携や書類作成もアドバイスがあるので、ひとりで悩まずに済みます。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
家庭だけで頑張るのではなく、すららのコーチや学校と連携しながら取り組めることで、保護者も「見守る」立場に専念でき、心に余裕が生まれます。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
すららを活用して自宅学習をしている不登校のお子さんにとって、出席扱いの制度はとても心強いものです。
ただし、この制度をうまく活用するためには、いくつかの重要な「注意点」を押さえておく必要があります。
学校や教育委員会に認めてもらうには、家庭だけの努力では限界があることも。
実際の現場では「制度を知らない先生」や「資料不足によって判断されにくいケース」なども見られます。
ここでは、すららを利用して出席扱いを申請する際に、保護者が気をつけておきたいポイントを丁寧にご紹介します。
ちょっとした配慮や事前準備で、制度のスムーズな活用につながりますよ。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
出席扱いを認めてもらうには、学校側の理解と協力が欠かせません。
すららを知らない先生もまだ多く、保護者が「これは文科省のガイドラインに基づいた学習ツールなんです」と説明していくことが求められます。
特に担任だけで判断できない場合も多いので、教頭先生や校長先生への早めの相談も視野に入れておきましょう。
すらら公式が発行している「教育委員会や学校向けの案内資料」などを持参すると、よりスムーズに話が進むケースが多いです。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
「ICTを活用した在宅学習=出席扱い可」という文科省の方針に沿った内容であることを伝えると、学校側も前向きに受け入れてくれる可能性が高まります。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
担任だけでは判断が難しい場合も多いため、保護者のほうから「資料がありますので、教頭先生や校長先生にも共有いただけますか?」と伝えておくと丁寧です。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
すべてのケースで必要というわけではありませんが、不登校の原因が体調不良や精神的ストレスに基づいている場合、医師による診断書や意見書が求められることがあります。
とくに、在宅学習が「本人にとって適切な学習環境である」ことを第三者の立場から証明する目的で、学校や教育委員会が書類提出を求めることがあるのです。
提出にあたっては、あらかじめ通っている小児科や心療内科に相談しておき、学習の様子や家庭での意欲も具体的に伝えておくことがポイントです。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
体調やメンタルの不調が理由で登校できない場合、医師の見解を示すことで学校側が「出席扱い」と判断しやすくなります。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
医師にあらかじめ目的を伝えることで、必要な内容を含んだ診断書を作成してもらいやすくなります。
すららでの学習内容も伝えておくと◎です。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
「教材を使って毎日継続している」「学習意欲はある」など、家庭での取り組みを医師に共有することで、より肯定的な診断文になりやすくなります。
注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱い制度では、「家庭での学習が学校と同程度の内容・時間で行われていること」が前提になります。
つまり、すららを使っているからといって、好きなときに10分だけ勉強すればOKというわけではありません。
学習内容は、学校の教科書に準じたものである必要があり、時間的にも授業時間に近づけることが望まれます。
すららは文科省の学習指導要領に準拠しているため、その点は安心ですが、学習時間や教科バランスには家庭での配慮が必要です。
特定の教科だけを集中的に学ぶよりも、全教科を満遍なく進めることで、より学校に準じた学習環境として認められやすくなります。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
家庭学習の質も問われるため、「ワークを自己流でやった」などでは不十分。
文科省に準じた教材(すららなど)を使い、計画的に取り組んでいることが重要です。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
すべての時間を机に向かって過ごす必要はありませんが、午前中に1時間・午後に1時間など、「生活リズム」に組み込むと提出書類でも評価されやすくなります。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
出席扱いは「総合的な学習」として判断されるため、国語・算数(数学)・英語だけでなく、理科や社会も含めて取り組む姿勢が求められます。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱い制度をスムーズに利用するには、「家庭と学校が学習状況を共有していること」が大前提となるケースが多いです。
すららでは学習レポートがダウンロードできるため、それを毎月学校に提出するだけでも「学習の継続性」がアピールできます。
また、学校側から面談や家庭訪問の依頼があった際は、できる限り対応しましょう。
担任の先生とは、定期的にメールや電話で進捗を伝えるだけでも「きちんと取り組んでいる」と伝わりやすくなります。
学校側が不安を感じないような、密な連携が大切です。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
家庭学習の様子を「学校が知っている状態」であることが出席扱いの前提になるため、連絡帳や保護者のメモなども役立ちます。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららには学習履歴や進捗状況をPDFで出力する機能があります。
月ごとに提出しておくと、学校側の記録にも残りやすくなります。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
先生の訪問や面談依頼がある場合は、「協力的な家庭である」と認識してもらう絶好のチャンス。
可能な限り、前向きに応じる姿勢を見せましょう。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
月1のレポートに加えて、「今週はここまで進みました」「○○に苦戦しています」などを伝えると、先生もサポートしやすくなります。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
自治体によっては、出席扱いを正式に認めるために、学校だけでなく教育委員会への申請が必要になる場合があります。
その場合は、学校を通じて書類を提出することがほとんどですが、保護者の協力も求められることがあります。
学習レポートや医師の診断書、意見書などが必要になることもあるため、事前に「どういった資料が必要ですか?」と学校に確認しておくと安心です。
教育委員会からの審査を通過すれば、より公的な形で出席扱いが認められるため、進学や転校時にも有利になります。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
学校単独で判断できない場合、教育委員会への説明用として書類提出が必要になることも。
学校と二人三脚で準備していくのが理想です。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
すららを使って不登校中も自宅学習を続けているお子さんにとって、「出席扱い」を認めてもらえるかどうかは将来の進路に関わる大事なテーマです。
ただ、制度の存在を知っていても「実際どう動けばいいの?」「どうすれば認められやすくなるの?」と迷う保護者の方は多いと思います。
そこでここでは、すららを使って出席扱いを成功させるために、実際に効果的だったとされる行動や工夫を「成功ポイント」としてご紹介します。
小さなことの積み重ねが、大きな信頼につながりますよ。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
すららはすでに全国の多くの学校や教育委員会で、出席扱いとして認定された実績がある教材です。
まだこの制度を知らない学校や、前例がないからと慎重になっている先生に対しては、「実際に他校で認められた例があること」を伝えると説得力がグッと増します。
すららの公式サイトには具体的な導入事例や、出席扱いの成功事例が掲載されているため、それを印刷して持参するのも効果的です。
学校側が「うちだけじゃないんだ」と安心できる情報は、大きな後押しになります。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
「他の自治体や中学校でも認定されている」という事実を見せることで、前例がない不安を和らげられます。
先生の気持ちに寄り添った伝え方を意識するとよりスムーズです。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すららの導入実績ページは、出席扱いを検討している学校への信頼性を高める材料になります。
印刷して資料と一緒に渡すと、後から校内で回覧もしやすくなります。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
出席扱い制度の審査では、「学習に対して本人が前向きであること」が重要視されます。
ただ親が「頑張っています」と言うだけでなく、実際に本人がどんな気持ちで学習しているのかが伝わるようなアクションを取りましょう。
たとえば、学習の感想や「今週の目標」などを本人が書いて提出することで、先生たちにも意欲が伝わりやすくなります。
また、面談などがある場合には、本人もできる範囲で同席し、自分の言葉で「続けたい」「がんばってる」と伝えると、印象が大きく変わります。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
自筆のメモや一言日記でもOK。
「今日できてうれしかったこと」など本人の気持ちが見えるものは、学校側の心を動かすきっかけになります。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
保護者が話すだけでなく、本人の声で「ちゃんと勉強しています」と伝えられると、先生の印象がガラッと変わります。
無理のない範囲で同席がおすすめです。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱いを認めてもらうには、単発的な学習ではなく「継続して学んでいる」ことが大前提になります。
だからこそ、無理なく継続できる学習計画を最初にしっかり立てておくことが重要です。
すららには専任のコーチがいて、子ども一人ひとりの特性や生活リズムに合ったスケジュールを一緒に考えてくれます。
特に、不登校で生活リズムが不安定になっているお子さんには、「朝は1単元だけ」など小さなルーティンから始めると続けやすいです。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
毎日少しずつでも「続けられる」ことが最大のポイントです。
張り切って詰め込みすぎるよりも、地道にコツコツ積み上げられる計画が信頼を得やすくなります。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
プロの視点で「無理のないスケジュール」を組んでもらえるのはすららの大きな強み。
継続しやすい学習設計は、出席扱いの申請でも大きな武器になります。
ポイント4・:「すららコーチ」をフル活用する
すららには、ただ教材を提供するだけでなく、専任の「すららコーチ」がついてサポートしてくれます。
出席扱いの申請に必要な学習記録やレポートの作成にも協力してくれるので、保護者がひとりで頑張る必要はありません。
コーチは子どもの学習進度を把握してくれているため、学校への提出用に「何をどうまとめたらよいか」を具体的にアドバイスしてくれます。
こうした第三者のサポートがあることで、学校側も「しっかりした体制で学んでいる」と安心してもらいやすくなります。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
すららコーチが作成を手伝ってくれる学習レポートは、出席扱い申請時の「信頼の証」として大きな力になります。
必要書類の整備も相談できるのが心強いです。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。
でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。
時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。
イライラして何度も怒ってしまっていましたが、
すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。
完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。
タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。
キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。
教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。
他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
不登校のお子さんを支える家庭学習において、「すらら」は出席扱いとして認定される教材のひとつとして注目されています。
ですが、実際に制度を活用しようと思った時に出てくるのが「何が条件?」「本当に出席としてカウントされるの?」という疑問の数々。
加えて、「うざいという噂が気になる」「料金や退会方法は?」といった利用前の不安もありますよね。
ここでは、すららに関する保護者の方から寄せられることの多い質問をまとめて、ひとつひとつ丁寧にお答えしていきます。
不登校でも安心して続けられる家庭学習のために、ぜひ参考にしてくださいね。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららに対して「うざい」といった口コミが出るのは、ごく一部の利用者が感じた「サポートの頻度」や「アニメキャラの演出」が合わなかったケースがあるからです。
対話型アニメ授業や、学習を後押しする連絡サポートが豊富なのは、メリットでもありますが、「自主性を重視したい」「干渉されたくない」と感じるタイプの子には合わない場合もあります。
ただし、実際には「サポートが心強い」「褒めてくれるから続けやすい」という好評も多数。
使い方やお子さんの性格に合わせて、うまく活用していくのがポイントです。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには「発達障害専用プラン」という名称のコースはありませんが、ADHDやASD、LDなど発達障害に配慮したユニバーサル設計がなされています。
料金は発達障害の有無にかかわらず一律で、特別な割引制度などは用意されていません。
そのかわり、合理的配慮として「短時間学習」「音声調整」「つまずき解析」などを全員が受けられる仕組みになっているのが特長です。
療育手帳を持っていても追加サポート料金は不要で、通常の月額費用の中ですべて対応してくれます。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
はい、すららは文部科学省が定めた「ICTを活用した家庭学習の出席扱い制度」の条件に沿った設計となっており、実際に全国の多くの学校で「出席扱い」として認められた実績があります。
必要な手続きとしては、担任の先生や学校長との事前相談、学習計画や記録の提出、必要に応じた医師の意見書の提出などが求められる場合がありますが、すらら側もその手続きをサポートしてくれます。
安心して使える教材のひとつです。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは、時期によって入会金が無料になったり、お得な特典が付いてくる「キャンペーンコード」が配布されていることがあります。
キャンペーンコードは、公式サイトや紹介ページ、時にはメールマガジンなどで告知されることが多く、申し込み時に専用フォームに入力すれば簡単に適用できます。
適用漏れを防ぐためにも、申し込み前にコードの有無をチェックしておくと安心です。
入会金が11,000円→無料になることもあるので、利用しない手はありません。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららを退会・解約する場合は、Webサイトやメールでは手続きできません。
専用の電話窓口「すららコール」に連絡する必要があります。
オペレーターに「解約希望日」「登録者情報」を伝えることで手続きが完了します。
日割り計算はないため、月末まで利用できる形です。
解約後は自動的に課金は止まりますが、完全にデータ削除を希望する場合は「退会」も併せて依頼することになります。
余計な引き止めもなくスムーズに解約できますので、安心してください。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
基本的には、すららの料金は「入会金+月額受講料」のみで、教材費やシステム利用料などの追加料金はかかりません。
紙の教材の購入も不要で、すべてタブレットまたはPC上で完結します。
家庭にある端末で利用可能なので、機材費も不要なのが魅力です。
兄弟で利用する場合も、同一契約で追加料金なしでの併用が可能です。
ただし、個別にオプションを申し込んだ場合のみ費用が発生するケースがあるので、契約内容は事前に確認しておくと安心です。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
はい、すららでは「1契約=1家庭」として扱われるため、兄弟・姉妹での利用が追加料金なしで可能です。
それぞれにマイページや進捗記録がつくため、兄弟それぞれのペースで学習できるのも嬉しいポイント。
たとえば小学生と中学生で教科・レベルが違っていても問題ありません。
無学年式の教材なので、兄弟ごとに合った内容で使えるのも魅力です。
家庭での学習コストを抑えながら効果的に使いたい方におすすめです。
すららの小学生コースには英語はありますか?
あります!すららの小学生コースには、英語が標準で含まれています。
アルファベットやフォニックスといった基礎から始まり、リスニング・スピーキング・文法・単語までバランスよく学べるカリキュラムが組まれています。
アニメーションやネイティブ音声も使われており、「聞く・話す」力を育てたいご家庭には特におすすめ。
英検5級〜3級程度までの対応も可能で、将来的な受験や中学英語への橋渡しとしても役立ちます。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららの最大の特徴のひとつが「すららコーチ」の存在です。
このコーチは、子ども一人ひとりの進度や性格に応じて学習計画を立ててくれるほか、つまずいた箇所への対処法、やる気が下がったときの声かけ、保護者との相談まで幅広くサポートしてくれます。
保護者が毎日管理しなくてもよいのがメリットで、「親がつきっきりにならなくて助かる」という声も多数。
まさに、家庭学習の伴走者のような存在です。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
家庭で学べるタブレット教材はたくさんありますが、「不登校の子どもでも出席扱いになるかどうか」という視点で選ぶと、実はその対応は教材ごとに大きく異なります。
中には学力補強には最適でも、学校との連携が想定されていないものもあります。
そんな中で「すらら」は、文部科学省のガイドラインに沿った設計で、実際に出席扱いとして認められた事例が多数あるのが大きな強みです。
ここでは、他の人気家庭用タブレット教材と比較しながら、すららがなぜ不登校家庭にとって信頼できる選択肢なのかをわかりやすく解説していきます。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
不登校の子どもが「すらら」で学習している場合、それが学校の「出席扱い」として認められる可能性があることをご存知でしょうか?これは文部科学省が定めた「ICT教材を活用した在宅学習の出席認定制度」に基づくもので、条件を満たせば学校の出席日数にカウントされる制度です。
ただし、出席扱いを認めてもらうには、学校との連携や正しい申請手順を踏むことが不可欠です。
このセクションでは、制度の概要から申請方法、注意点や成功させるためのコツまで、すべてまとめて詳しく解説していきます。
不登校家庭にとって安心できる学習環境を整えるために、ぜひご活用ください。
